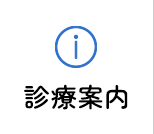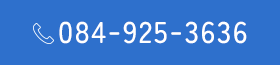当院の小児眼科について
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだはっきりと「見る」力は備わっておらず、明暗が分かる程度ですが、乳幼児期になると視力は飛躍的に発達します。
生後1ヶ月から8歳ごろまでを視力の発達の感受性期といい、この期間に適切な視覚刺激を受け取ることで視力は大人と同程度まで発達します。
逆に、何らかの原因で適切な視覚刺激を受け取ることできないと、視力の発達が止まったり遅れたりして弱視という状態になります。
当院では、年齢に応じた視力の発達について、しっかりと確認してまいりますので、気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。
このような仕草や行動はありませんか?
小さな子供は目の症状をうまく表現できませんが、子供の仕草や行動でわかることがあります。
以下のような症状がありましたら、目の病気が隠れている可能性がありますので、一度眼科で調べてもらうことをお勧めします。
- テレビや本の距離が近すぎる
- 顔を傾けたり、横目で物を見たりすることが多い
- あごを上げてものを見る
- よく目を細めて物をみている
- 目をしきりに擦っている
- よく眩しそうにしている
- 片目の塞ぐと極端に嫌がる
- 黒目が揺れているように見える
- よく転ぶ、よく物にぶつかる
- めやにや涙が多い
- 目線が合ってなくてどこを見ているかわからない
- 黒目の真ん中が白く光って見える
学校検診で異常を指摘された方へ
学校で行われる視力検査は0.3、0.7、1.0の3つの指標を用いて、A〜Dの4段階で判定する「370方式」と呼ばれる方法で行われます。
A判定(視力1.0以上): 教室の最後列からでも黒板の文字が問題なく読める視力
B判定(視力0.7以上1.0未満): 教室の真ん中から後ろの席であれば、黒板の文字は読めるが、小さい文字は読みにくい視力
C判定(視力0.3以上0.7未満): 教室の真ん中よりも前の席でないと、黒板の文字が半分程度しか見えない視力
D判定(視力0.3未満): 一番前の席でも、メガネやコンタクトレンズを使わないと黒板の文字がはっきり見えない視力
学校検診の視力検査は、簡易的な方法で行われるため、視力低下の原因や詳しい状態までは分かりません。
学校の眼科検診で異常を指摘された場合は眼科を受診し、精密検査を受けましょう
学校から渡された用紙をお持ちの上、受診してください。
小児眼科で診療する疾患
弱視
 弱視は、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が十分に得られない状態のことです。
弱視は、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が十分に得られない状態のことです。
眼鏡やコンタクトで矯正して1.0以上になる場合は、弱視とは言いません。6歳をすぎると弱視治療をしても視力が改善しにくくなるため、なるべく早期に発見して、治療を開始したい病気です。
弱視の原因により治療法がおこなりますので、弱視になっている原因を早く見つけることが大切です。
弱視の種類の原因
屈折異常弱視
近視・遠視・乱視が強いとものがはっきりと見えずボケて見えます。ボケた像ばかり見ていると視力の発達
が妨げられ弱視になります。近視の場合は近くのものははっきり見えるため、弱視になりにくいと言われていますが、非常に強い近視の場合は弱視になる可能性もありますので注意が必要です。
治療は、近視・遠視・乱視を矯正する弱視用眼鏡を装用することです。治療のポイントはなるべく長い時間、度のきっちり合った眼鏡をかけて、はっきりした像を見ながら日常生活を送ることです。適切な度数の眼鏡を装用しなければ、はっきりとした像を見ることができませんので、視力が十分育ちません。お子様の成長に合わせて眼鏡の度数変更が必要になりますので、定期的な眼鏡チェック、診察が必要になります。
不動視弱視
遠視・近視・乱視に左右差が強いためにおこる片目の弱視です。はっきり見える方の目ばかりを使い、見えにくいの方の目を使わなくなるため視力の発達は不十分になります。片目の視力は正常に発達しているため、日常生活に不自由はなく、周囲からは全く判りません。3歳児健診や就学時健診で片目だけ視力が悪くてみつかるケースが多いです。
治療は、近視・遠視・乱視を矯正する弱視用眼鏡を装用することです。弱視眼の視力改善が悪い場合は、見える方の目を目隠しして、見えにくい方の目だけではっきりと物をみる訓練をします。見える方の目を隠している時だけゲームをしてもよいなど、目を使って集中できるルール作りをすると効果的です。適切な度数の眼鏡を装用しなければ、はっきりとした像を見ることができませんので、視力が十分育ちません。お子様の成長に合わせて眼鏡の度数変更が必要になりますので、定期的な眼鏡チェック、診察が必要になります。
斜視弱視
斜視が原因で起こる弱視です。斜視とは右目と左目の視線が違う方向へ向いている状態です。斜視があっても右目と左目を交互に上手に使っていれば弱視になりませんが、片方の目ばかりを使って、反対の目の視線が常にずれていると、その目にははっきりとした像がうつらないため弱視になってしまいます。
治療は見える方の目を目隠しして、見えにくい方の目で物をみる訓練をします。視線のズレが大きい場合は、より視力を発達させるために、斜視手術を行うこともあります。その場合は全身麻酔が必要になりますので、治療のできる施設へ紹介させていただきます。
形態覚遮断弱視
白内障や眼瞼下垂などにより、目の中に十分に光が入ってこないことで弱視になります。新生児〜乳児の間に光刺激を十分受けていない目は視力の発達が悪くなるため、適切な治療をおこなっても弱視になることが多くなります。
治療は原因となる白内障や眼瞼下垂など手術を行い目の中に光が入ってくるようにすることです。手術が終わった後も眼鏡などの弱視治療が必要になります。専門的な手術、弱視治療が必要となるため対応できる施設へ紹介させていただきます。
斜視
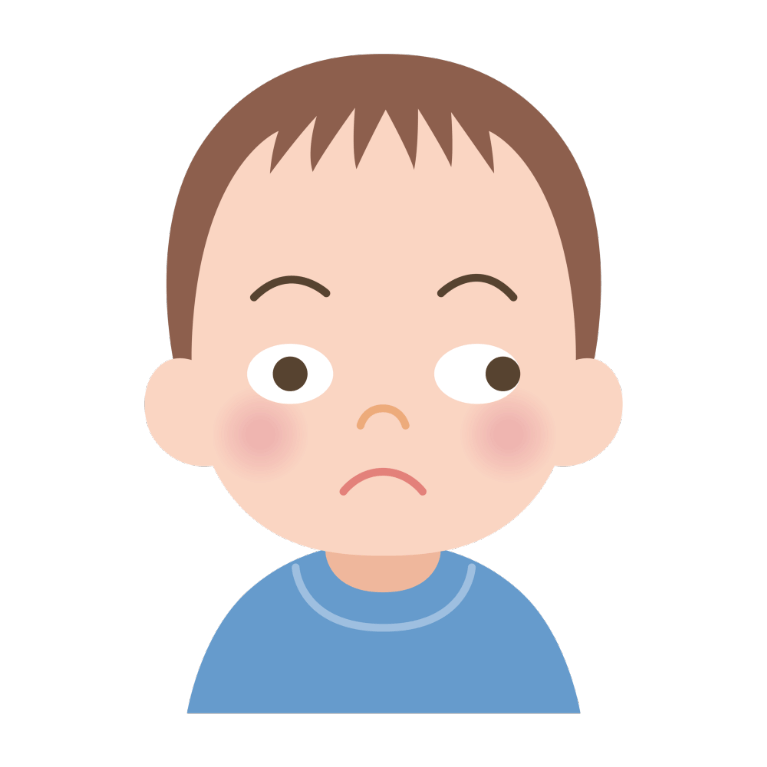 通常、物を見る時は右目と左目の視線は同じ方向へ向いています。
通常、物を見る時は右目と左目の視線は同じ方向へ向いています。
斜視とは右目と左目の視線が違う方向へ向いている状態です。まっすぐに物をみると二重に見えるため、顔を傾けたり、横目で物をみたりすることで視線のズレを直そうとする行動が見られることがあります。斜視があっても右目と左目を交互に上手に使っていれば問題ありませんが、片方の目ばかりを使って、反対の目の視線が常にずれていると、その目にははっきりとした像がうつらないため弱視になってしまう可能性があります。
原因
斜視の原因としては、目の筋肉や神経の異常、遠視、脳の病気、全身の病気に伴うものなどがあります。ほとんどは目を動かす筋肉や神経の異常や遠視によるものですが、最近はスマートフォンやゲームの過剰使用が原因で発症する内斜視が増えてきています。
治療
斜視の治療の第一目標は弱視にならないことです。弱視になっている場合は、遮蔽訓練や斜視手術が必要になります。次の目標は視線の向きを揃えてあげることです。原因によって治療は異なりますが、遠視が原因であれば眼鏡処方になります。顔を傾ける癖が残ったまま成長すると顔の形が歪むことがあり、手術で視線を矯正してあげる方がよいことがあります。斜視の種類によって、手術が必要かどうか、何歳のときにどのような手術を行うかなどが異なってきます。
近視
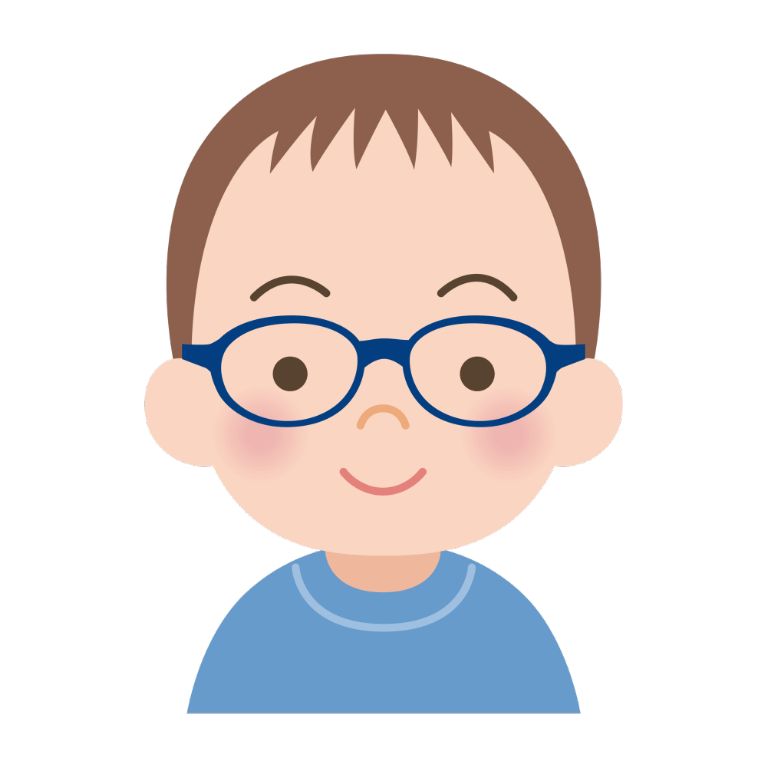 近視とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結ぶ状態です。手元はよく見えますが、遠くはぼやけて見えます。子供の成長と共に目の長さ(眼軸)も長くなるので近視は進行します。
近視とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結ぶ状態です。手元はよく見えますが、遠くはぼやけて見えます。子供の成長と共に目の長さ(眼軸)も長くなるので近視は進行します。
近視が強くなりすぎると眼球に引き伸ばされ、将来、緑内障になりやすくなったり、網膜裂孔や網膜剥離など様々な病気を発症しやすくなります。現在、世界的に近視が増加しており、そういった病気を増加を予防するため、近視抑制治療が注目されています。日本ではまだ保険診療で近視抑制治療は行えませんが、治験は行われており、一部の近視抑制治療は保険診療になる見込みです。当院では、自由診療にはなりますが、近視抑制治療にも力を入れりますので、お気軽にご相談ください。
原因
近視は、遺伝的要因と環境的要因が関係して起こります。
親が近視である場合、子供は近視になりやすくなります。また、環境面では、字を書くときや本を読む時の距離が近い、長時間のテレビ、スマホ、ゲームの視聴がリスク因子として挙げられます。
一方で屋外で活動する、遊ぶことは近視抑制効果があると言われています。
治療
眼鏡・コンタクトレンズ
近視は治療するのではなく、眼鏡やコンタクトレンズで矯正するのが一般的です。根本的な治療ではありませんが、眼鏡やコンタクトレンズの度数は変えることができますので、成長に合わせて調整することができます。
近視抑制治療
近視は目の長さ(眼軸)が長くなった状態です。一度伸びてしまった眼軸は基本的には短くはならないので、成長と共に眼軸が伸びてくるのをいかに抑制するかが重要になります。当院では、自由診療にはなりますが、近視抑制治療にも力を入れりますので、お気軽にご相談ください。
はやり目
 その名の通り、非常にうつりやすい(流行りやすい)結膜炎で、アデノウイルスに感染することで発症します。
その名の通り、非常にうつりやすい(流行りやすい)結膜炎で、アデノウイルスに感染することで発症します。
症状には個人差がありますが、ひどい人では強い充血、涙が止まらない、眩しい、痛みがでて瞼が腫れることもあります。伝染力が非常に強いため、大抵は数日以内に反対の目にも結膜炎を発症します。
治療
アデノウイルスに有効な目薬はありませんので、他の結膜炎を併発することを防ぐため抗生剤点眼と炎症を抑えるためのステロイド点眼を処方します。ウイルスをやっつけるのではなく、症状を緩和するための治療ですので点眼開始後も1〜2週間症状は続きます。
注意点
- 感染力が非常に強く、タオルやドアノブなどの感染者が触れたであろうものを介して他の人にもうつります。手洗いをしっかりする、タオルの別々のものを用意するなどして感染対策をしましょう。
- 結膜炎の炎症が強いと症状が落ち着いた後に黒目に斑点上の濁りがでてくることがあります。しっかり点眼をして完全に治癒するまで通院が途絶えないようにしましょう。
- 学校保険法で指定される学校感染症のひとつです。医師から許可がでるまで保育園、幼稚園、学校への登校は控えるようにましょう。
先天性色覚異常
 先天性色覚異常は男の子の5%、女の子の0.2%程度に見られる比較的多い病気になります。
先天性色覚異常は男の子の5%、女の子の0.2%程度に見られる比較的多い病気になります。
すべての色がわからないわけではなく、識別しにくい色があるなど、その症状や程度は人によって様々です。パイロット、電車運転士、警察官、消防士、自衛官など、特定の仕事への就業が制限されることから、自分の色覚異常の種類や程度を知っておくことも大切になります。識別しづらい色を知り、適切に対処すれば日常生活に大きな支障はありません。
原因
先天性色覚異常は、遺伝が原因となります。
治療
有効な治療方法はありませんが、識別しづらい色を知り、適切に対処すれば日常生活に大きな支障はありません。
ただし、パイロット、電車運転士、警察官、消防士、自衛官など、特定の仕事は色覚異常の程度によっては資格を取ることができません。