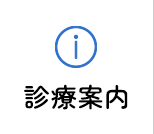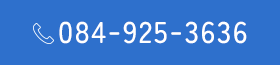かすんで見えづらくなる「黄斑浮腫」とは?
 目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。
目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。
黄斑とはその網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。黄斑部が障害されると、視界のちょうど真ん中の部分が障害されることなり、細かい物を判別したり、文字を読んだりすることができなくなります。
黄斑浮腫とは、黄斑部に血液や血液成分が溜まり、浮腫が生じる病気です。黄斑浮腫になると視界がかすみ視力が低下し、物が歪んで見えるようになります。
黄斑浮腫を起こす病気として、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、ぶどう膜炎などがあります。詳細についてはそれぞれのリンクをご参照ください。
ぶどう膜炎とは
目の中にある虹彩、毛様体、脈絡膜といった血流が豊富な組織をぶどう膜といいます。このぶどう膜に何らかの原因で炎症が起こっている状態をぶどう膜炎と呼びます。
原因は多岐にわたり30以上あると言われており、原因を特定できないものも多くあります。原因により、ぶどう膜の中でも炎症が強くなる場所が異なってくるため、黄斑浮腫だけでなく、硝子体が濁ってかすんでみえたり、虹彩に炎症が起きて目がひどく充血したり様々な症状がでます。原因に応じた治療が必要になります。炎症が強い場合はステロイドの点滴、内服、注射、点眼を併用することがあります。
黄斑浮腫の治療
黄斑浮腫が続くと、光を感じる細胞である視細胞が傷つき、視機能が回復しなくなる場合もあります。
黄斑浮腫の原因が糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症などはっきりしている場合は、レーザー治療や抗VEGF療法を行います。ぶどう膜炎のように原因がはっきりしない場合にはステロイドによる治療が主体となります。
ステロイド注射
炎症を抑える効果のあるステロイドを眼球の周囲(テノン嚢下)に注射します。
効果が不十分な場合はステロイドの内服や免疫抑制剤の内服を行うことがあります。
硝子体手術(硝子体生検)
内科的治療が無効で、硝子体の濁りが強い場合などは原因検索のため、硝子体を生検して検査に提出することがあります。硝子体中に含まれる炎症物質を同時に除去することで黄斑浮腫が軽快することもありますが、確実性に乏しく、濁り除去による視力改善と生検による診断が主な目的となる治療です。